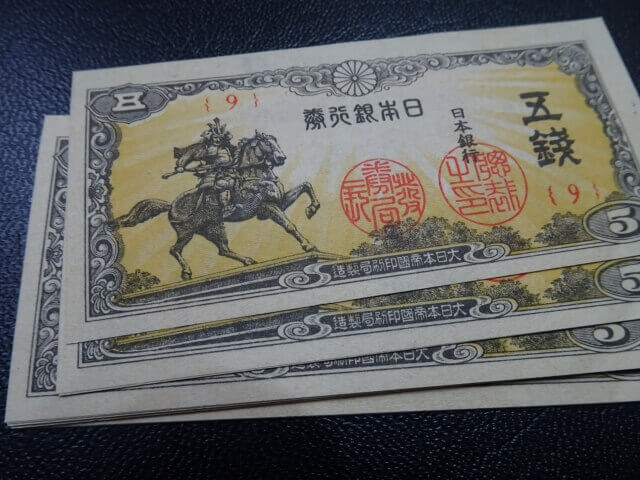プレミア100円札ってあるの?100円札の種類と買取相場

古銭の処分に困っている方、自宅を片付けていたら昔の「100円札」を発見した!
という方、古銭の買取に興味のある方へ。
100円札の正しい買取相場を知って、無駄なく賢く買い取ってもらいませんか?昔よりも古銭をコレクションする人が減り、買取需要を少しずつ下がってきてはいますが、それでもプレミアがつくものは今でも高値で取引されています。
100円札と聞くと見慣れないし、古いお金だとすぐ分かるので買取相場もそれなりに期待しちゃいますよね。
ですが100円札でも発行枚数が多いもの、市場やオークションによく出回っているもの、状態が著しく悪いものなどは査定のマイナスポイントとなり、額面とほぼ一緒の価値になってしまう場合もあります。
自分の今持っている100円札はプレミアなのかどうか、どれくらいの買取相場になるのか、100円札買取の気になるポイントをまとめてみましたので一緒にチェックしてみましょう。
100円札をはじめとする古銭の買取や査定依頼なら古銭に関する正しい知識を持った査定員が在籍しているバイセルがおすすめ。バイセルは1日あたり700件近くの買取依頼がある上場企業で、古銭の販路をたくさん持っているため高価買取に期待する事が出来ます。
100円札の種類と買取相場について
100円札(正式名称/百円紙幣)は明治18年~昭和49年まで製造・発行された日本銀行券の1つとなっており、発行時期によって8つの種類があります。
デザインや素材も異なり、透かしが施されているものもあります。
それぞれの種類の特徴を見てみましょう。
①旧百円券(日本銀行兌換銀券)
明治18年(1885年)発行、昭和14年(1939年)に通用停止となった旧百円券。
表面には大黒像が描かれており、別名「大黒札」とも呼ばれていました。
漢数字の記番号、3~4桁の通し番号が書かれていて、エドアルド・キヨッソーネ(イタリア)が図案製作者となっています。
発行はすでに終了しており、もともとの発行枚数も非常に少ないため希少価値の高い種類となっています。
市場にはほとんど出回らず、おそらく現存している数は数枚と予想されます。
コレクターの注目度にもよりますが、数十万円以上の買取額がつく可能性もあり。
②改造百円券(日本銀行兌換銀券)
明治24年(1891年)発行、昭和14年(1939年)に通用停止となった改造百円券。
表面には藤原鎌足が描かれており、裏面は彩紋となっています。
旧百円券の強度を上げるためにコンニャクの粉を混ぜて製造された紙幣があったのですが、ネズミなどに食べられてしまう被害が多数あった為にこの改造百円券が作られました。
記番号は漢数字、5桁の通し番号となっています。
紙幣の大きさは日本で発行された紙幣の中で一番大きく、全体的な発行枚数は旧百円券と同じく少ないです。
ですので現存数も数枚しかないと予想され、見つけた場合は額面をはるかに上回る買取額が期待できるでしょう。
通称「めがね100円」。
③甲号券(日本銀行兌換券)
明治33年(1900年)発行、昭和14年(1939年)に通用停止となった甲号券。
表面には藤原鎌足と談山神社がデザインされており、日本銀行と書かれた裏面が紫色の模様をしていたので「裏紫100円」の別名があります。
前期と後期で記番号の形式が異なり、後期の甲号券にはアラビア数字が採用されていました。
紙幣のプレミアは珍しいナンバーである事も多いので、文字数字並び次第で数万以上の査定額が狙える場合もあります。
今は失効券となっていますが、コレクターの間でも根強い人気があり、買取需要もありますので買取を依頼する価値はあるかと思います。
④乙号券(日本銀行兌換券)
昭和5年(1930年)発行、昭和21年(1946年)の通用停止となった乙号券。
表面には聖徳太子と夢殿が描かれており、通称「1次100円」と呼ばれています。
聖徳太子が描かれた100円券は全部で4種類あり、そのうちの1種類目がこの乙号券となるんですね。
乙号券と似たデザインの100円札もあるので素人目ではその価値や種類を見極めるのは難しく、またキレイな状態で残っている事も少ないので買取相場がハネ上がらない事もしばしば。
気になる方は自分で価値を判断せず、古銭の買取査定ができる方に見てもらうようにしてくださいね。
⑤い号券・ろ号券・A号券(日本銀行券)
昭和19年(1944年)~昭和31年(1956年)に製造・発行された100円札。
表面のデザインは共通して聖徳太子が描かれており、額面も100円(百圓)となっています。
乙号券が1次100円と呼ばれており、それに続いてい号券が2次100円、ろ号券が3次100円、A号券が4次100円と呼ばれていました。
い号券は乙号券の聖徳太子と比べてわずかに表情の違いがあり、A号券は乙号券のデザインとほぼ一緒となっているので見極めるのが難しくなっています。
ろ号券は真ん中に聖徳太子のみ描かれており、夢殿はセットになっていません。
どれも記されているナンバーや印刷ミスによってプレミア度が変わり、買取相場も大きく変動します。
⑥B号券(日本銀行券)
昭和28年(1953年)発行、昭和49年(1974年)に通用停止となったB号券。
表面には板垣退助、裏面には国会議事堂が描かれています。
今の100円硬貨になる前、最後の紙幣タイプの100円で現在でも使用することが可能となっています。
ただし、古いお金なのでお店によっては使用を断られる事もあります。
自動販売機などでは使えません。
全体的な大きさは今までのものよりも少し小さくなります。
プレミア100円札を狙え!
~板垣退助の100円札~
比較的新しく、持っているという方も多い板垣退助の100円札(B号券)なら、自宅や倉庫で発見できるチャンスがありますよね。
そんな板垣退助の100円札がプレミアになると額面以上の高額買取が期待できちゃうんです!
ポイントは「製造エラー」。
印刷ミス、透かし、耳つき。
どれも紙幣としては不良品になるのですが、古銭買取の世界ではプレミアとなり高額査定になりやすくなるんですね。
まず《印刷ミス》は、お札の余白部分の幅が均等でないズレて印刷されてしまった100円札で、目で見て分かるほどズレているものもあれば、じっくりチェックしないと分からない程度にズレているものもあります。
《透かし》は、本来きちんと印刷されていなければならない部分が透けてしまっているエラー紙幣でこれも見極めるのが難しくなっています。
《耳つき》は印刷ミスではなく裁断ミスで、100円札の表面の四隅のいずれかに紙片が残っている状態のものを指します。
残り具合は様々ですが、印刷ミスや透かしよりもややプレミア度が高くなります。
これらのエラー100円札になると古銭としては最近まで見慣れていた板垣退助の100円札でも買取相場がグンと上がり「100.000円」前後となる場合が多いです。
まとめて所持している場合はぜひ、1枚1枚デザインをチェックしてみてくださいね。
100円札の査定には古銭買取専門のサイトがおすすめ
通常のものとプレミアとなるものが混在する「100円札」の価値を知りたいなら、自分でチェックするよりも古銭買取の専門サイトにお願いするのがオススメ。
100円札の買取相場を種類毎に把握している専門のスタッフが1枚1枚丁寧に査定してくれるので、納得のいく査定額になりやすいんです。
専門サイトというように実店舗は持たず、ネット内で申し込みや相談ができるのでわざわざ足を運ぶ必要もありません。
近場に古銭を買い取ってくれる業者がないという方にもオススメです。
プレミアの可能性がある100円札をお持ちなら、サイトを覗いてみるだけでもやってみると良いですよ。